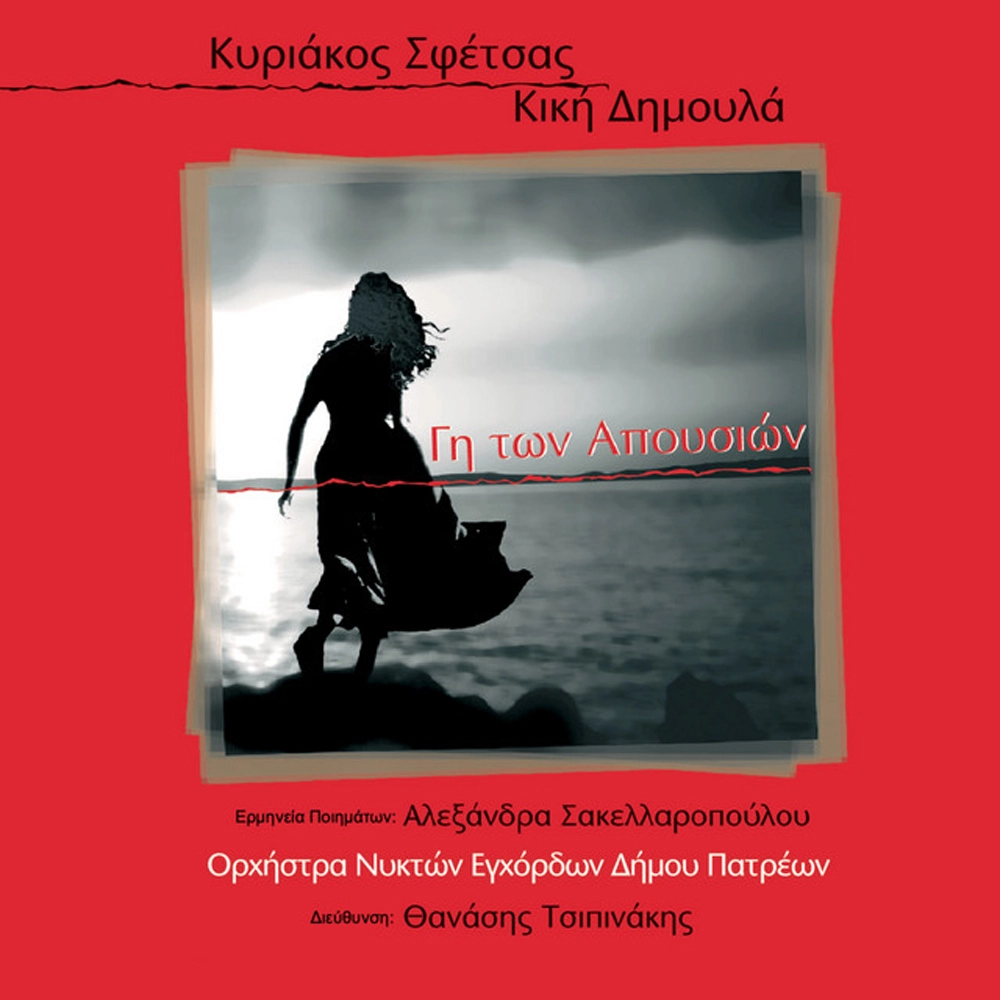ジャンルの“偏見”を壊してくれた1枚 | ディスクユニオンスタッフが教える、かけがえのない音楽 # 21
連載第21回目となるテーマは、「ジャンルの“偏見”を壊してくれた1枚」
各ジャンルを担当する音楽マニアならではの深い知識と独断と愛情にあふれるリコメンドを楽しんでほしい。ここで見つけたディスクユニオンの“推し”が、あなたにとってかけがえのないライブラリーになることを願いつつ。
サイケとパンクの境界線を歩く祈りの音「VINE OF SOULS」
recommend by ディスクユニオン 横浜西口店 清水 斉容さん
横浜西口店パンク担当。民俗音楽やレゲエも好きです。
アーティスト名:IOWASKA
アルバム名:VINE OF SOULS(2001年/ALTERNATIVE TENTACLES)

スタッフのおすすめコメント:
UKのバンドで70'sサイケデリックの真髄を持つハードコア。おそらくホークウインドやグレイトフルデッドが00年代に出てきたらこういう感じになるのかもしれない。どうやらアナーコパンクバンドAMEBIXの曲で聴こえてくる女性の声はこのバンドのボーカルのようで醸し出す雰囲気が最高なんです。ストーナー的、スラッジ的にもトリップできてしまう。さらにレゲエまで取り入れている素晴らしき作品。
3曲目の“AYAHUASCA”(アヤワスカ)というタイトルはIOWASKAと同義で、それは「魂のつる」と呼ばれる南米のアマゾン川流域に自生するキントラノオ科のつる植物。主に先住民族がシャーマニズムの儀式や民間療法に用いるもので、それはまさにサイケデリックな世界そのもの。これはパンク/ハードコアからサイケやエクスペリメンタルを行き来できてしまう異彩を放つ名盤です。
メロウな夜を彩る、都会派シティポップの原点「Relief 72 Hours」
recommend by 商品部門 物流担当 稲垣 吉人さん
気になったものは何でも試しに聴く者です。メタル、パンク、プログレ、フリージャズ、サントラ、実験音楽など。一番好きなミュージシャンは浅川マキ。
アーティスト名:国分友里恵
アルバム名:Relief 72 Hours(1983年/RVC)

スタッフのおすすめコメント:
ジャンルの偏見というほど強いニュアンスではないのですが、自身がシティポップ系を聴くようになったきっかけを作った作品で真っ先に思いつくのはこちらです。AOR/シティポップ方面の音楽ライター、金澤寿和氏によって2004年に刊行され、2013年と2017年に再版されているガイド本、『Light Mellow和モノSpecial』にて大きく掲載されていたこの作品。
折しもこのアルバムも2013年に初CD化され、自身もどことなく引っ掛かりを覚えていたので購入・視聴。1曲目の1音目から都会の夜景を思わせるキーボードの音程とファンクなリズム、山下達郎や竹内まりやのツアー・レコーディングメンバーも務めた経験のある国分氏の歌唱力はこのデビューアルバムの時点で実力派の風格あり(後のアルバムで更に凄い事になる)。
その後の楽曲もブラックコンテンポラリー系統の優れたナンバーが並び、それらを支えるのは和モノを始めとする数多くの名作に参加する名プレイヤーの名前がズラリ(今剛、井上鑑、村上ポンタ秀一、青山純、高水健司、富樫春生ら多数)。プロデューサーには林哲司と一切の隙なし。2013年以降レコードでもアンコールプレスされるなどようやく然るべき地位を得たと言える大傑作です。
ダウナーな裏の顔が光るラップ世界「Tele倶楽部」
recommend by ディスクユニオン 川崎店 若山 有沙さん
川崎店にいます。なんでもききます。
アーティスト名:ピーナッツくん
アルバム名:Tele倶楽部(2021)

スタッフのおすすめコメント:
ピーナッツくんはVtuberでもありながらラッパーとしても活動しています。紹介したいのが2021年リリース「Tele倶楽部」。このアルバムは、様々な女性Vtuberやクリエイターを客演に迎えた楽曲を収録。ピーナッツくんと女性Vtuberの声の相性はバッチリで聴いていて気持ちがいい!普段のテンション高めのキャラクターとは違ってラッパーのピーナッツくんはダウナー。ギャップが感じられてさらに魅力的。Vtuberの曲なんてオタクチックなものでしょう?、そんな偏見を壊してくれる1枚です。
また、RECORD STORE DAY 2024でアナログリリースされた「Special Days feat.藤井隆&ピーナッツくん」もオススメ。Joint Beautyの甘いビートにピーナッツくんの遊び心のあるリリック、それらすべてを包み込む藤井隆さんの歌声はきっとあなたを癒してくれます。Vtuberの曲だから、と思わずとりあえず聴いてほしい。気に入る1曲が見つかるはず。そして是非ピーナッツくんの動画も観ていただきたい。
鍵盤で紡がれる王妃たちの叙事詩「The Six Wives Of Henry VII」
recommend by ディスクユニオン 新宿ロックレコードストア 島崎 かれんさん
クラシック(オペラ等)の演奏活動をしている傍らユニオンで働いております。70年代米国ロック,CITY POP,プログレが好きです。
アーティスト名:RICK WAKEMAN (YES)
アルバム名:The Six Wives Of Henry VII(1973年/A&Mレコード)

スタッフのおすすめコメント:
「イエス」キーボーディストとして知られるリック・ウェイクマンの1stソロアルバム。
「プログレッシブ・ロック」と聞くと曲が長く難解なイメージを持つ方も多いと思います。
そんな先入観を打ち破る情熱的でありながら繊細な表情を見せる作品です。
題材は英国王ヘンリー8世と6人の妻達。宗教音楽、クラシック、ジャズ、ロックなどさまざまなジャンルの要素が絡み合い6人の妻達がたどった悲痛な運命を描いていきます。まさに「プログレッシブ」の名にふさわしい作品。
規律正しく、無機質なリック・ウェイクマンの鍵盤プレイからは理性の中の情熱を感じます。
レコーディングには「イエス」や「ストローブス」のメンバーをはじめとした総勢18人ものミュージシャンが参加。特に最終曲’Catherine Parr’でのビル・ブルーフォードのドラムは圧巻の一言。
個人的には第5曲の"Anne Boleyn 'The Day Thou Gavest Lord Hath Ended'がお気に入りで、ハードな一面を見せたと思ったらクラシカルな一面も見せてくる楽曲.リックのテクニカルな鍵盤プレイも大注目です。
本作品のようなプログレの作品は精密に計算され構成されており、一つのジャンルや演奏スタイルにとらわれず様々な要素を取り入れているので様々な音楽ジャンルのファンの方々にも楽しめる作品だと思います!何より名作なので色々な方に聴いていただきたいです。
雨音に溶ける少女たちの叫び「She's Rain」
recommend by ディスクユニオン お茶の水駅前店 古田 翼さん
日本とUKのニューウェーブ、ポストパンク、ポジパン好きなFC東京サポーターです。
アーティスト名:BELLRING少女ハート
アルバム名:She's Rain(2023年/Lonesome Record )

スタッフのおすすめコメント:
今回のテーマが「ジャンルの“偏見”を壊してくれた1枚」という事で私が選んだのはこの1枚。BELLRING少女ハート(通称ベルハー)の紹介を簡単にすると、2012年結成し2016年に一度活動休止、2023年に新体制として活動再開している東京のアイドルグループである。この作品は新体制としての初のフィジカルで、新曲の「She's Rain」と過去曲3曲の再録が収録されている。アイドル、と聞くとキラキラでポップなイメージを抱くが、このベルハーはそうではない。楽曲を聴けばすぐその概念は無くなるだろう。
雨音からピアノの音が入りドラムンベースで進んでいく「She's Rain」。イントロから暗く陰鬱な雰囲気で、まるで闇からの少女達の叫びのような楽曲の「low tide」。美しくも儚い旋律で進んでいく「ROOM 24-7」。まるで物語のエンディングソングのようなミディアムテンポの「或いはドライブミュージック」。この4曲を聴いていただくだけでもベルハーの魅力はわかるのだが、もしこれで聴いて良いな、と感じたらぜひ他の曲も聴いてほしいし、ライブにも足を運んでみていただきたい。私が思うにベルハーはロックだとかパンクだとかプログレだとかその他諸々のジャンルに位置づけすることはできず、「ベルハー」自体がジャンルであると思う。
国境なき音の詩学「Gi Ton Apousion」
recommend by ディスクユニオン 町田店 安齋 耕さん
先日は先輩の結婚式に一人だけメイド服で行きました。邦楽、ノイズ、アニソンなど担当。音大出身のツインテール♂
アーティスト名:Kyriakos Sfetsas & Kiki Dimoula feat. The Plucked String Orchestra Of The Municipality Of Patras, Fonitiko Synolo Iho & Alexandra Sakellaropoulou
アルバム名:Gi Ton Apousion(2003/The Hubsters)
スタッフのおすすめコメント:
クラシカルな調性、しかし前衛ジャズのタッチも残しつつ、その中で琴がリードを取っているような音色の主旋律と対旋律、影に徹しながらも緊迫感のあるドラムス、そこにスポークンワードと合唱が乗っかる。 古代密教の館で流れるようなサウンドトラック。
クラシック、現代音楽、劇伴、エレクトロ、レアグルーヴ、エクスペリメンタルなど多岐に渡る作品を発表している彼ならではの作品。詞(または詩)はギリシャの著名な詩人であるKiki Dimoulaによるもの。
いい音楽はいい音楽だ。宙から見れば国境などないように、コスモポリタニズムを言いたいわけじゃないが音楽の前では皆等しく赤子だということを我々に思い出させてくれる。私たちは何かにつけてカテゴライズし、ジャンルに分ける。(それがどんなに仕方のないことであっても)彼の音楽はそれを優しく諭すように遠くの地から批判してくれているようだ。
魔法のコラボが生んだ異色傑作「不思議の国のアグネス ~AGNES IN WONDERLAND~」
recommend by 商品部プログレ担当 祝前 伸光さん
にわかプログレファン。シティポップやアイドルも好きです。
アーティスト名:AGNES CHAN
アルバム名:不思議の国のアグネス ~AGNES IN WONDERLAND~(1979 / SMS)

スタッフのおすすめコメント:
アイドルソングに偏見を持っていました。音楽としてはどうなの、と、ろくに聴きもしないで考えていたのです。そんな偏見を壊すのに十分すぎるほどのインパクトのある作品が、アグネス・チャンの「不思議の国のアグネス~AGNES IN WONDERLAND~」です。1970年代を代表する女性アイドルのひとり、アグネス・チャンの14枚目のアルバムにして、ゴダイゴが制作を全面的にバックアップしGODIEGO feat.AGNESとさえ呼べるゴダイゴの隠れ名盤、そしてもっと言うなら日本のプログレとしての大傑作でもあります。
タケカワユキヒデ作の曲はキャッチーで親しみやすいメロディで、ミッキー吉野の煌びやかなキーボードアレンジと縦横無尽なプレイはアグネスの透明感のあるハイトーンのボーカルと相俟って、まさにワンダーランドへ誘われるようなマジカルな体験をもたらしてくれます。おかげでアイドルソングに対する見方が変わり、いまではすっかりアグネスの、そしてアイドルソングの大ファンになりました。
1979年リリースのオリジナルはもちろんアナログですが、CDにはタケカワユキヒデのデモバージョンが収録されたボーナスディスクとタケカワの思い入れたっぷりの制作秘話が付属する2枚組版と、全曲のカラオケバージョンをボーナストラックとして収録した紙ジャケ版と2種類あり、どちらもおすすめです。
音の記憶を織り直す原理主義「Endtroducing…」
recommend by 通販センター M.F.さん
通販センターアルバイトスタッフとして2024/11/1入社。10代半ばにHIPHOPを聴き始め、30年以上が経ちました。聴く音楽に関しましてはサンプリング・ソースとして使用される音に制限がないようにあまりジャンルを気にせず楽しんでおります。
アーティスト名:DJ SHADOW
アルバム名:Endtroducing…(1996 / Mo Wax)

スタッフのおすすめコメント:
ご存知の方も多いであろう本作は発表当時のアメリカではメジャーなヒップホップを好む層からの反応は薄く、テクノ等を好む層からの反響が大きかったようですがそれもそのはずで緻密な打ち込みによるインストゥルメンタルを軸に作品が進行し、抽象的かつ無機質な印象を受けるタイトルは一聴して理解出来る派手さ/幸福感への訴求とは程遠い所にある事を示唆しているかのようです。私自身も当時友人が聴かせてくれた際に「すごいな」と感じたもののすぐに購入し繰り返し聴くほどにのめり込むほどではなかった記憶があります。が、この作品を今聴いて感じるのはアーティストの「よい音楽であればその出自を問わない」、「ヒップホップはその発生当初から進化を繰り返し、音楽表現全般における可能性の境界線を押し広げてきた」という無言のメッセージです。
昨今サンプルソースをまとめたWeb上のデータベースも存在し、YouTubeでも今作品の全サンプルソースを作品と並行して紹介している動画がありますので興味のある方はご覧いただければより本作についての理解が深まり楽しめると思いますが、ディープ・ファンクとオルタナ/プログレ/メタルや韓国産ロック、コンテンポラリークラシック、ゴスペル、ジャズをフレーズで抜き出し編み込むようにハーモニーと展開を作り出し、新旧のヒップホップのラインや映画のワンシーンのセリフを随所に挟み込んだ作りに驚愕します。これはかつてNYのダンスコミュニティの為にブロック・パーティでアフリカ・バンバータがダンサブルな音楽としてKraftwerk “Trans Europa Express”やYMO “Firecracker”を2枚使用しミックスしていた事実や、メイン・ソース“Breakinfg Atoms”において複数のサンプルを重ね合わせ新しいグルーヴを作り出したラージ・プロフェッサーのプロダクションと重なります。つまり本来あるべき形へ意識して「先祖返り」する「ヒップホップ原理主義者」の傑作という事で長文にお付き合いいただき本当にありがとうございました。
酒と詩と反骨のフリースタイル「Thrill Of It All」
recommend by 通販センター M.F.さん
通販センターアルバイトスタッフとして2024/11/1入社。10代半ばにHIPHOPを聴き始め、30年以上が経ちました。聴く音楽に関しましてはサンプリング・ソースとして使用される音に制限がないようにあまりジャンルを気にせず楽しんでおります。
アーティスト名:ECD
アルバム名:Thrill Of It All(2000 / Cutting Edge)
スタッフのおすすめコメント:
劇団に所属、ロックに傾倒したのち、「クラブ」や「DJ」が今ほど一般的ではなかった頃からそのキャリアをスタートし、生活のため肉体労働に従事する傍ら90年代HIPHOPの日本における隆盛に後進のアーティストをフックアップする他裏方としても文字通り多大なる貢献を果たした御大のメジャーレーベル作品。御本人も当時のインタビューにて語っているように「過去の作品が売れて印税がかなり入ってきて、(肉体労働などの)仕事をしなくてもいいし酒を一日中飲むようになった」との事でそれまでのオーソドックスな作風とは打って変わって非常に自由な発想が炸裂している作品です。このタイトルの前後に発表している作品はどれも素晴らしいです。今作はそのなかでも特に気に入っている作品です。
この作品から1年後に「ECD PRESENTS 君は薔薇より美しい」がひっそりと?リリースされます。そのあまりにも逸脱したスタイル〜完全なるアルコール中毒状態からの入院〜が災いしたのか次作である「Season Off」を最後にエイベックス系列であるカッティング・エッジとの契約が終了します。以降も自主制作にて精力的に音源を発表、執筆、社会運動家としても活動されましたが2018年末期がんにより永眠されました。この作品を聴いた当時は先述の病状などは知らず「なんだかよくわからないけどとにかくヤバい、オリジナリティが凄い」と戦慄を覚えた記憶があり、その印象は今も変わりません。
独創的なネタと音使いといい、イルドーザーが手掛けたグラフィックといい「自分は今こういうのが楽しい」という感覚を共有できる周辺の人脈とこのような作品を作り上げた所に私の評価のポイントがあります。声も非常に力強く、文字通り命を削って音楽を作っていたのだなと感じずにはいられません。プロモーション用に作られたLP盤が存在します。「ロンリー・ガール」を聴いたことがある貴方には、本作はどのように聴こえますか。
音と知性が戯れる即興の旅「AN ADVENTURE OF INEVITABLE CHANCE / 素晴らしい偶然を求めて」
recommend by 通販センター M.F.さん
通販センターアルバイトスタッフとして2024/11/1入社。10代半ばにHIPHOPを聴き始め、30年以上が経ちました。聴く音楽に関しましてはサンプリング・ソースとして使用される音に制限がないようにあまりジャンルを気にせず楽しんでおります。
アーティスト名:ヤン富田
アルバム名:AN ADVENTURE OF INEVITABLE CHANCE / 素晴らしい偶然を求めて(2000/Audio Science Laboratoly)
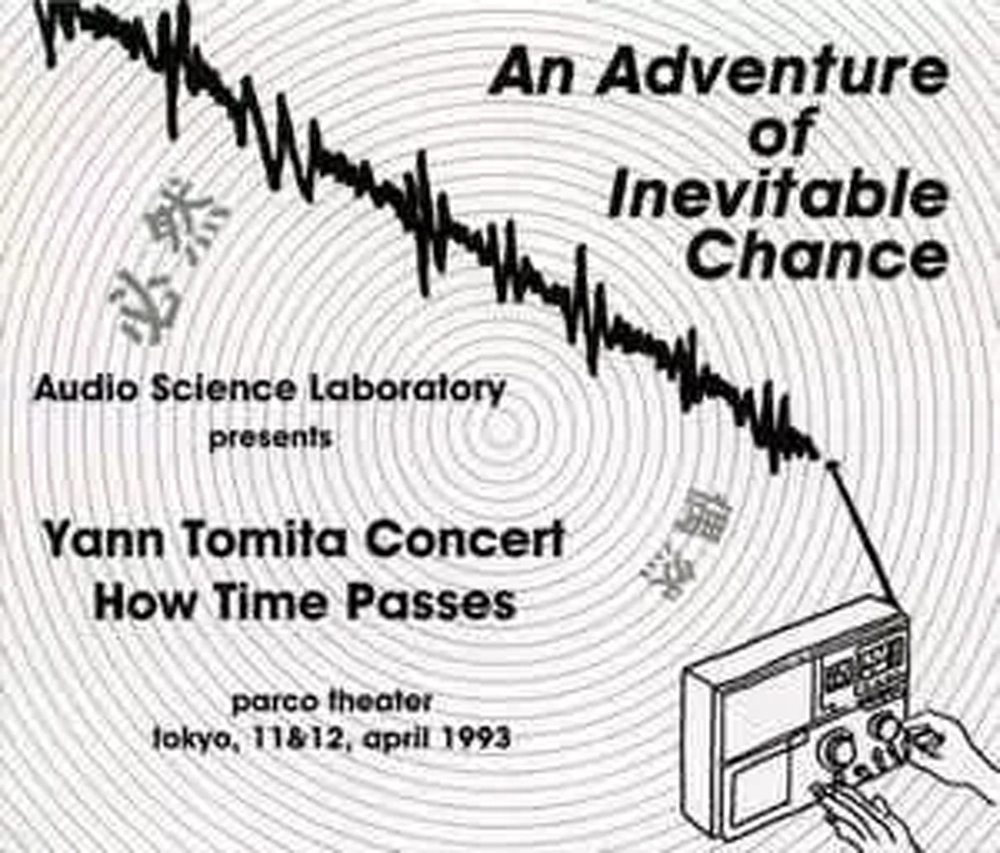
スタッフのおすすめコメント:
WATER MELON GROUPとしての活動、いとうせいこう「MESS/AGE」のプロデュース等日本のクラブ・ミュージック黎明期からその現場に携わっている氏のライブ・アルバムです。私は「東京ブロンクス」という曲をきっかけにその存在を知りましたがその時点でとんでもないプロダクションの質とハイセンスさにその存在を忘れることができませんでした。1989年にヒップホップが非常に可能性に満ちた音楽である事を理解し自己に取り込む先見性と、作品へ昇華する際の完成度が尋常ではありません。そんな氏の今作はコンセプチュアルな発想を軸に様々な楽器/音が出るモノを駆使した「楽しんで聴く実験音楽」となっております。
もはや一般の方が想定する「演奏」や「音楽ジャンル」から逸脱したコンセプト重視の作品が中心ではありますが、突然にシンプルかつ明るいフレーズが差し込んでくる所に氏の人間味と優しさ、音楽家としてのバランス感覚を感じます。今作は比較的聴きやすい作品となっておりますのでよく晴れた日のドライブにもってこいの一枚です。それでは素敵な一日をお過ごしください。
「DIVE INTO MUSIC.」に込められた想い

世界中どこにいても同じ音楽を楽しむことができる今の時代に、ディスクユニオンは違和感を感じています。なぜなら、本来音楽というものは、ひとりひとりが自らの手で触れて、自らの脚で探して出会うべきものだからです。だからこそ私たちディスクユニオンは、見たことのない曲、聴いたことのない世界を求め、音楽の海へ飛び込んでいきます。そしてこの想いを「DIVE INTO MUSIC.」というスローガンに込め、お客様と共有して参ります。
diskunionHP:https://diskunion.net/
公式youtube:https://www.youtube.com/@diskunion_official
instagram:https://www.instagram.com/diskunion/
前回の記事はこちらから
「リバイバルヒットの謎」をテーマにおすすめアーティストをご紹介
- Edit : Yusuke Soejima(QUI)