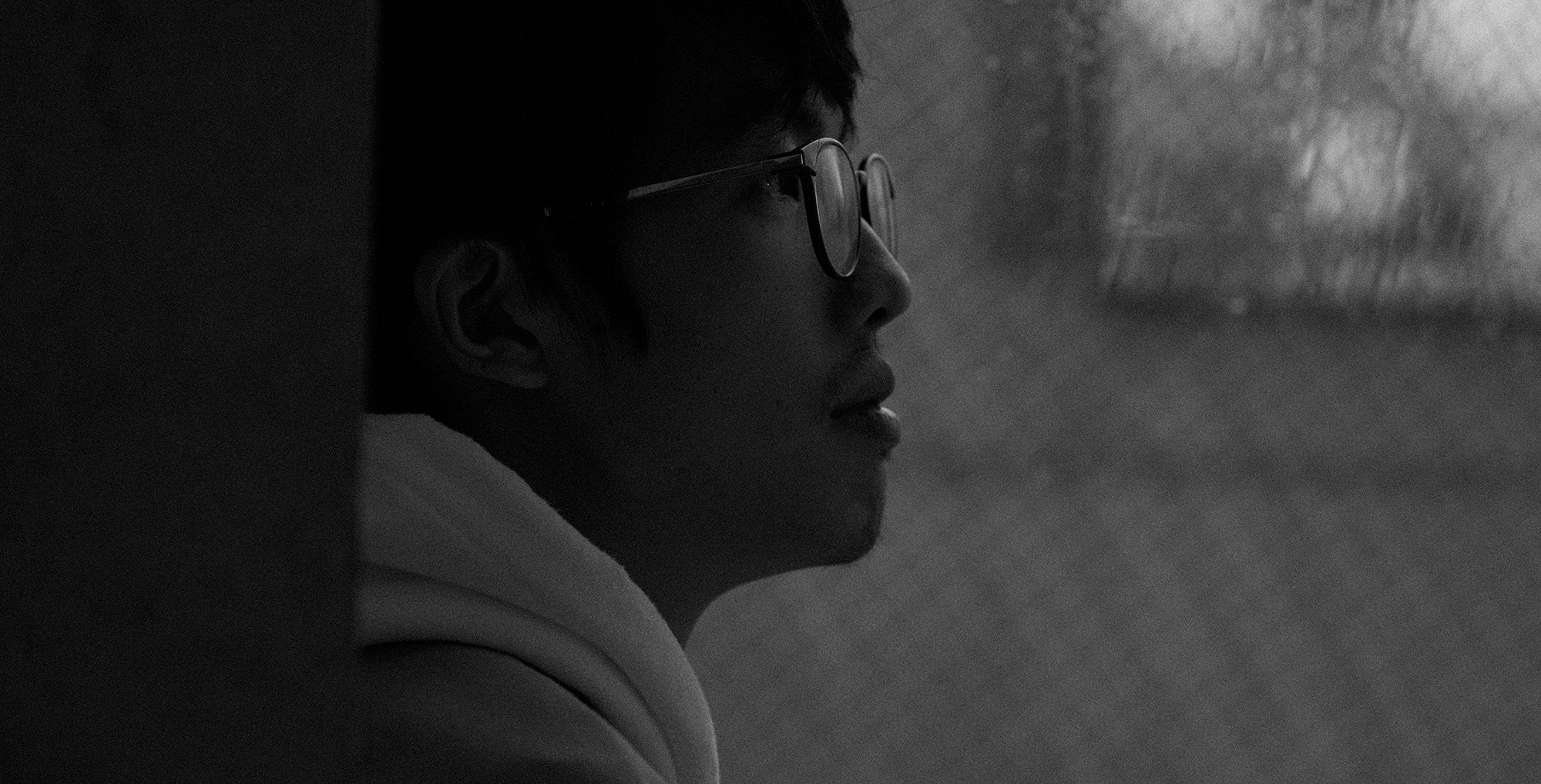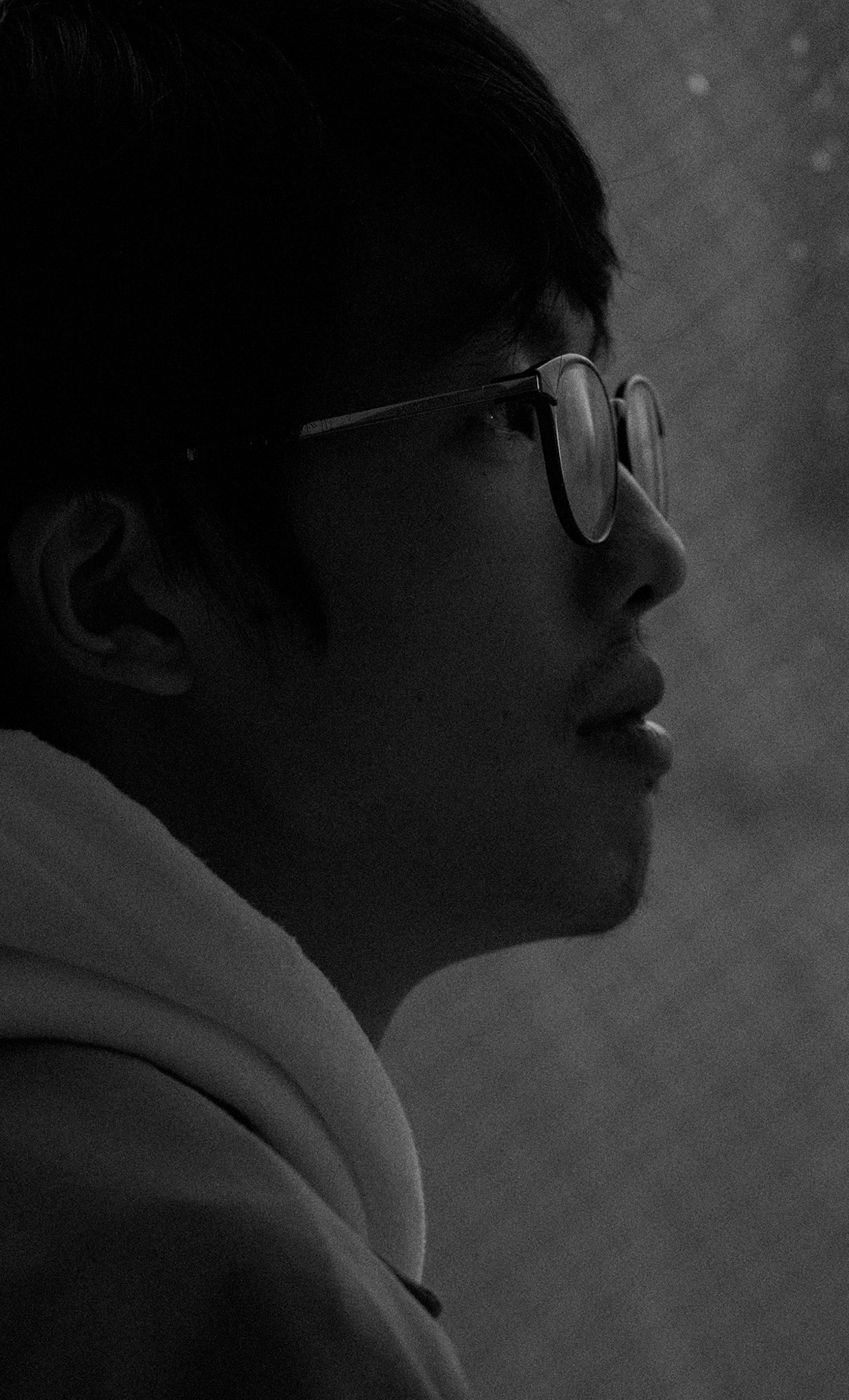小島央大 – 嘘はつかない
ものづくりの過程は、建築も映画も共通している
— 1994年に神戸で生まれて、その後ニューヨークで育ったそうですね。
母親が化粧品のデザイナーで、その仕事のためにニューヨークに渡りました。
— お父さんも一緒に?
はい。父親は専業主夫として。その前は音楽業界にいたんですけど。
— クリエイティブな家庭環境だったんですね。現在の小島監督のクリエイティブマインドに繋がるような原体験はありますか?
映画でいうと、ニューヨークで映画撮影をしているのをよく見かけました。とくに印象に残っているのは、ウィル・スミス主演の『アイ・アム・レジェンド』。ニューヨークに誰もいなくなるという映画なんですけど、それを実際の街でやっていて。
あとは住んでいたのがロウアー・イースト・サイドというアーティストが多い下町だったので、そこらじゅうに小さなギャラリーがあったり、パフォーマンスをしていたり、親の知人にもアーティスティックな人が多かったり。
— 街と文化が融合していて、なんともうらやましい環境です。
通っていた小学校もちょっと変わってて、クリエイティブ重視で。授業の時間を少なくして、創作の時間を多めにとるという。
— 創作の時間というのは?
基本的にはフリータイム、自由にやれと。提供された素材を組み合わせておもちゃを作ったり、毎週「これを作ろう」という課題に取り組んだり。だから日本に戻ってきて、みんなまじめだなあと。クラスに一体感があって、おもしろかったですけど。
— 日本の環境にもすぐに適応できたんですね。言葉は問題なかったですか?
中学二年生の夏にアメリカの学校を中退して、日本の学校に入る翌年の4月までの半年間、父親がスパルタで教えてくれました。日本語は親としかしゃべっていなかったので、漢字や文法、発音などを覚えるのが大変でしたね。
— 読み書きはとくにきつそうですね。
7年分の漢字を4カ月ぐらいで詰め込みました。

— 帰国後、中高を経て東京大学工学部建築学科に進学。もともとかなり勉強ができたんですか?
いや。親からは大学なんて行く必要ないよと言われていて。本当は音楽をやりたくてバンドサークルの多い早稲田大学に行きたかったんですけど、お金がないから公立で東大しかアカンと。それはたぶん『ドラゴン桜』の影響だと思うんですけど(笑)。
でもたしかに東大に行って損はないし、英語ができたんで他の人より1科目勉強しなくていいし、建築学科には興味があったんで勉強して。4点足りなかったら落ちたくらいのギリギリで滑り込めました。
— さらっと言ってますけど、並大抵の勉強じゃ入れないですよね。建築のどういうところに惹かれますか?
小学生のころから模型やレゴをよく作ってて。模型を作るという作業自体が好きですね。そして建築が人間に及ぼす影響が不思議でおもしろく感じます。
— でも大学の卒業後、建築の道には進まなかった。
建築家になるのはすごく長い道のりですが、まわりにはそこにすべてを注ごうとする意識が感じられる人たちがいて。でも自分は違うな、彼らに任せた方がいいなと。それで自分はなにをやるのかすごい悩んだ末に映画の魅力に気づいて、監督業をやりたいと。
— すごくジャンプしていますよね。建築から映画へ。
ジャンプしているようで、建築って映画に近いんです。考える要素が多くて、カオスの中からビジョンを作るっていう。アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥというメキシコの映画監督も、インタビューで「建築と映画は似ている」と言っていて。
建築だったらデザイン、構造、設備、法律など、建築家というディレクターのもとさまざまなチームがひとつのものを作ろうと動いていく。映画も同様に監督が思い描いているものを、カメラや音声、ヘアメイク、スタイリングなどいろんな要素が組み合わさって作りあげられていく。ものづくりの過程は、建築も映画も共通しているように感じています。
— その共通点は、映像の世界に入る前に気づいたんですか?
そうですね。それで映像に進む自分にも納得できました。チームでものを作るということが、僕のやりたいことだなと。山にこもって陶芸とかはできない……。
— なるほど(笑)。
総合芸術としての映画の可能性を感じた
— 映像のキャリアを、映像作家の山田智和さんのもとでスタートされていますが、どういったご縁があったのでしょうか?
もともと山田さんの撮ったサカナクションのMVなどを観ていて好きな方だったんですが、たまたま山田さんがツイッターでアシスタントを募集していて。山田さんからは「やめておいた方がいいよ」と忠告されたんですが(笑)。映画を撮るタイミングまで、1年半ぐらいお世話になりました。
— 山田さんから学んだことは?
山田さんは映像に対する愛がある人で、何かに愛を注ぐことって素敵だなって。自分がやりたいことに対してひたむきに向きあっていくことが一番大切で、そうすると同じような情熱を持った仲間が自然に増えていくんじゃないかなと。技術的なところよりは、映像に対する姿勢が学びでした。
— 情熱を持ち続けるのっていうのも才能ですよね。小島さんは嫌になることはないですか?
編集はだるいなって(笑)。単純に大変。たとえば80時間ぐらい撮って、それを2時間にするのってどうすればいいんだって途方に暮れたことも何度もあります。でも映像を撮ること自体は楽しいことだし、その楽しさがある限り挫折はしないです。作るということが楽しくなくなったら、それはやめるときなのかなって。

— では逆に、映像制作で一番好きなところやテンションが上がる瞬間は?
一番好きなところはロケハン。いろんな場所を訪れて、そこにある可能性を想像するのが探検みたいでおもしろいし、撮影前で気が楽というか。一番テンションが上がるのは撮影の現場で、「これが真実だ」ってフィクションがリアルになる瞬間があるんです。
— 撮ってるときに「撮れた」とわかるんですね。映画を撮ろうと思ったのはいつからですか?
きっかけのひとつが大学4年生のときに観たアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督の『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。全編ワンカットに見える映画で、総合芸術としての映画の可能性をすごく感じたんです。どんな芸術も人生に影響を与えますが、映画は2時間で世界観や没入感を作り出すという独特のやり方でそれを実現していて。
それに映画自体がメディアとして独立しているところが好きで。たとえばMVも好きですけど、やっぱり元となる曲自体がよくないとダメですよね。最終的にはスパイク・ジョーンズみたいに、映画を撮りつつMVもCMも撮るみたいなことができたら夢のような生き方だなと。
— 映画というメディア自体に対してどういう新しいアプローチができるかということを考えている?
そうですね。基本は、観たことのないものを作るということ。そうでないと、その映像の長期的な価値がなくなってしまう。感じたことのない感動や感情、気づきがあることで、観た人が良い方向に転んでいけば価値があるなと思っています。
映画ってわりと最近できたメディアだから、どんどん進歩していて。技術的にも、物語を映像にするってことに対しても、まだまだ無限の広がりを感じています。
— 映像の師匠が山田智和さんだとしたら、映画の師匠はだれですか?
映画の師匠はいないですが、考え方で影響を受けているのはテレンス・マリック監督でしょうか。もともと哲学を専攻していた人で、映画を通して哲学していて。映画作りは、あるテーマに対して作り手は3年間考えて2時間の作品に仕立て、それを観た人がまた考えるということが一連になっている。テレンス・マリックはそれをわかりやすくやっていて。その生き方が好きです。
— 映画を作ること自体が哲学することに繋がる。
作り手も作品を観た人も、結果的に世の中に対する理解を深め、発見に繋がることが素敵ですよね。
価値観を決めつけず、人それぞれの人生を理解する
— 2021年11月20日(土)には、初の長編監督作品『JOINT』が公開されますが、長編映画って撮ろうと思っても撮れるもんじゃないですよね?
もともと短編映画は撮っていて、それに関わってくれたキャストともっとやりたい気持ちがあって。それであるとき飲み会に山本一賢さんが来てくれて、盛り上がった次第です。
— 次第で(笑)。
俺たちは映画を作らなければいけないんだっていう義務感というか圧倒的な情熱があって、とりあえず作ろうとなりました。
— それはいつのことですか?
2018年の夏から企画が始まって、オーディションをたくさんして、キャストが集まってきて。クランクインは2019年の2月です。

©小島央大/映画JOINT製作委員会
— すごく見応えのある作品でした。日常を描いたような作品に比べて、ハードルの高さは感じませんでしたか?
普通に大変でしたけど、そこにハードルの高さは感じて無くて。しっかりとしたリサーチとキャスティングと普遍的なテーマ性があればいいものができるんじゃないかなと、クライム映画の魅力と可能性を感じていました。逆に日常系でおもしろい映画を作る人ってすごいなって尊敬します。
— アウトローたちが描かれていましたが、小島監督自身は彼らにシンパシーを抱いていますか?
よくない人たちだなと思いつつも、「俺はこれでしか生きられない」と生き様を決めている感じがよくて。『JOINT』で(山本一賢さん演じる)石神武司はそこが決められず中途半端で、だんだん自分の生き方を探していく。外から見ていると足を洗えばいいのにと思うけど、浅く考えて全否定せず、人それぞれの人生を理解することが大事というか。それってシンパシーなのかな?
— 近いかもしれません。
たとえばスケートボードって街を汚す文化のひとつだと思うんです。でもそれを僕は否定できなくて。好きだから。それに似ているかもしれないです。価値観を決めつけないことが、自分の中で倫理として重要だと思います。

©小島央大/映画JOINT製作委員会
— 今回『JOINT』を撮るにあたって大切にしたことはなんですか?
ひたすらリアリティのあるものを作りたいと思っていました。ヤクザ映画をモダンにするということに映画としての価値があるなと。和彫りを入れないとか、株で儲かってるとか、今のヤクザのリアリティを重視しました。
— 長編映画を実際に撮ったことで気づいたことはありますか?
一番大事なのは人間関係だなと。もちろんMVとかでもそうですが、撮影は1日で終わっちゃう。映画は長い分、家族的な付き合いになるので「人間関係とは?」という気づきがありました。
— 撮影期間はどれぐらい?
本撮影が4カ月ぐらい、それから飛び飛びで8カ月ぐらいあって、編集後には追撮を数日間やりました。
— ああ、長いですね。劇中で好きなシーンは?
刺青のシーンが好きです。あれは本当に入れていて、臨場感が出るなって。ニューヨークに住んでいる親友の親がタトゥー屋さんで、横でピザを食べながら刺青を入れているような環境なんです。日本だと刺青を入れるのってすごいアウトローというか反骨精神だと見なされるんですが、ニューヨークだと芸術表現としても認められていて。今回、撮っているときに神聖な時間だと感じました。瞑想に近い作業、彫り師が魂を入れ込む作業で、その行為自体にロマンがあるなと。
— あのシーンは音も記憶に残りました。まだ公開前ですが、『JOINT』をご覧になった方から反響は届いていますか?
一番多いのがすごいリアルだったという声。それは意図したところでもあるのでうれしいですね。あとは、エンタメっぽいのにアートっぽいということも言っていただいたり。エンタメとアートのバランスも重要視したところで、おもしろくて目が離せないような映画もいいですけど、僕は逆に眠くなるようなロシア映画とかにもすごく魅力を感じてて。そこを感じとってくれる観客がいたことはすごくうれしかったです。

©小島央大/映画JOINT製作委員会
— 小島監督はこれからも多くの作品を手掛けていくと思いますが、どんな映画監督になっていきたいですか?
大それたことは言えないんですけど、嘘はつかないようにしたいです。僕が作りたいと思うのは何かしら社会に結びついていることなので、自ずと次の作品もそういうテーマになってくると思ってて。人間的な部分を真っ正面から描いて、そこに嘘がないことが大事だなと。
もちろん映画自体が大きな嘘なんですけど、でもそのフィクションのなかにまぎれもない真実があるというのはいろんな映画を観てきて感じるので。「それこそ愛じゃん」って。そういったリアリティを大切にしていく監督でありたいと思います。
— 最後に、これから映画監督になりたいという方に向けてアドバイスをいただきたいです。映画監督になるためになにをすべきでしょうか?
この20年、技術的な進歩が本当にすごくて。カメラがすぐそこにあるし、YouTubeもあるし、Netflixもあるし、すごく恵まれている環境だと思うんです。今の若い人の方は映画を観れるチャンスが多いので、40年後の映画界はタランティーノみたいな人がたくさんいるおもしろい業界になるかもしれません。
だからたとえばスコセッシが好きならNetflixで観て、真似をして、iPhoneでどんどん撮ったらいい。映画製作について深く考えると大変そうだな、お金がかかるなとか壁がどんどん見えてくるんですが、撮り始めると意外と壁なんてないことに気づいてくる。そうはいっても撮れる人、撮れない人で分かれちゃうと思うんですけど、それも撮ってみないとわからない。撮れない人は、撮れないとわかったことで違う道も見えてくる。やっぱ始めないと、なにも始まりませんよね。

Profile _ 小島央大(こじま・おうだい)
1994年神戸生まれ。幼少からニューヨークで育ち、中学より帰国し、東京大学建築学部卒業後、映像の世界に飛び込む。映像作家の山田智和の下でアシスタントディレクターを1年半経て、独立。以後、MVやCM、企業VPやVJ、LIVEなど、ジャンルや形態に囚われず、アイデア豊かな様々な映像作品を監督。情緒的な演出と、映画的で上質な色使いを得意とする。これまで主に手がけてきた作品には、「BUMP OF CHICKEN - Small world MV」「NEWS - 未来へ MV」「amazarashi - 世界の解像度 MV」「Daiki Tsuneta x Pasha de Cartier」などがある。
Instagram Twitter
Information
映画『JOINT』
2021年11月20日より、渋谷・ユーロスペースほか全国順次公開
普段、我々が気軽に登録している個人情報が知らないうちに特殊詐欺のための名簿として売買されている実態をリアルに描いたクライムムービー。
監督:小島央大
出演:山本一賢、キム・ジンチョル、キム・チャンバ、三井啓資、樋口想現、伊藤祐樹、櫻木綾、鐘ヶ江佳太、林田隆志、宇田川かをり、平山久能、二神光、伊藤慶徳、片岸佑太、南部映次、尚玄、渡辺万美
©小島央大/映画JOINT製作委員会
- Photography : Yasuharu Moriyama(QUI / STUDIO UNI)
- Art Direction : Kazuaki Hayashi(QUI / STUDIO UNI)
- Text&Edit : Yusuke Takayama(QUI / STUDIO UNI)